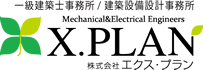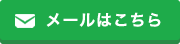省エネ関連
初のIoTはスマート照明?!知って驚くスマート照明の歴史
2018-09-22
カテゴリ:省エネ計算[照明]
最近巷で噂の「スマート照明」。
某大手家具販売店では、スマート照明が大ヒット商品になっているようですね。
ではスマート照明とは一体なんなのでしょう。
今回は、意外と知らないスマート照明の歴史をわかりやすくお伝えします。
某大手家具販売店では、スマート照明が大ヒット商品になっているようですね。
ではスマート照明とは一体なんなのでしょう。
今回は、意外と知らないスマート照明の歴史をわかりやすくお伝えします。
□スマート照明とは、スマートフォンと連動できる照明のことである
スマート照明とは、スマートフォンを用いて点灯・消灯・光量の調整等さまざまな操作ができる電球のことです。
蛍光灯、LED等さまざまなタイプがありますが、最近は世界中で省エネの機運が高まっているため、LEDタイプのスマート照明が人気です。
付属のリモコンで操作するものも含めて広義のスマート照明だと言われることもありますが、今回はスマートフォンで操作するものに限定してその特徴や歴史をご紹介します。
スマート照明とは、スマートフォンを用いて点灯・消灯・光量の調整等さまざまな操作ができる電球のことです。
蛍光灯、LED等さまざまなタイプがありますが、最近は世界中で省エネの機運が高まっているため、LEDタイプのスマート照明が人気です。
付属のリモコンで操作するものも含めて広義のスマート照明だと言われることもありますが、今回はスマートフォンで操作するものに限定してその特徴や歴史をご紹介します。
□スマート照明の機能とは
スマート照明の機能として、電球とスマートフォンをBluetoothで接続し、電球を使うシチュエーションによってスマートフォンで操作が可能になる、というところに最も大きな特徴があります。
明るさや色が変えられるという点では従来とあまり変わらないように思えますが、従来の機能を超えた機能があります。
スマート照明の機能として、電球とスマートフォンをBluetoothで接続し、電球を使うシチュエーションによってスマートフォンで操作が可能になる、というところに最も大きな特徴があります。
明るさや色が変えられるという点では従来とあまり変わらないように思えますが、従来の機能を超えた機能があります。
*タイマー機能
電球をつける時間を設定し、自動で点灯・消灯を行います。
例えば朝は真っ白な光で目を覚まし、夜家に帰ると部屋には赤みのある暖かい色みの光がついている、など、生活に合わせて光環境を設定できます。
これを使えば、消し忘れを防ぎ省エネに役立てることもできます。
電球をつける時間を設定し、自動で点灯・消灯を行います。
例えば朝は真っ白な光で目を覚まし、夜家に帰ると部屋には赤みのある暖かい色みの光がついている、など、生活に合わせて光環境を設定できます。
これを使えば、消し忘れを防ぎ省エネに役立てることもできます。
*気分で色を選んでくれる
「勉強したい」「リラックスしたい」等の要望に合わせて、部屋の照明を選択してくれます。
自分で明度や色を調節しなくても、目に適した適切な光加減が手に入りますね。
「勉強したい」「リラックスしたい」等の要望に合わせて、部屋の照明を選択してくれます。
自分で明度や色を調節しなくても、目に適した適切な光加減が手に入りますね。
□さて本題:スマート照明の起源は日本にあった?!
スマート照明の起源となったのは、東京大学の研究所で生まれた「TRONプロジェクト」です。
このプロジェクトは、実は個人にスマホが普及する30年も前に立ち上がったものでした。
スマート照明の起源となったのは、東京大学の研究所で生まれた「TRONプロジェクト」です。
このプロジェクトは、実は個人にスマホが普及する30年も前に立ち上がったものでした。
時を遡ること1984年、ちょうど個人のコンピューターが登場し、ファミコンが流行った時期ですね。
この年に、東京大学でネットワークを研究していた坂村健教授が、TRONプロジェクトを立ち上げました。
TRON(The Realtime Operating system Nucleus)とは、ネットワーク化したコンピュータをあらゆるところで機能させ、利用するシステムのことです。
この年に、東京大学でネットワークを研究していた坂村健教授が、TRONプロジェクトを立ち上げました。
TRON(The Realtime Operating system Nucleus)とは、ネットワーク化したコンピュータをあらゆるところで機能させ、利用するシステムのことです。
これを開発するために取り組んだ研究をまとめてTRONプロジェクトと言います。
このチームで最終的に建設した「TRON電脳住宅」では、ITを用いて天候や気温、日射等を自動的に計測し、その分析結果に合わせて室内の環境を整えられるように、自動で空調をコントロールし、窓やカーテンの開閉、照明の調整をすることができました。
現代と違ってコンピュータは個人には手が出せないほど高価だったため、民間で実用化されることはありませんでした。
このチームで最終的に建設した「TRON電脳住宅」では、ITを用いて天候や気温、日射等を自動的に計測し、その分析結果に合わせて室内の環境を整えられるように、自動で空調をコントロールし、窓やカーテンの開閉、照明の調整をすることができました。
現代と違ってコンピュータは個人には手が出せないほど高価だったため、民間で実用化されることはありませんでした。
しかしこれが元で、ビニールハウス内の自動温度調整機能などが作られ、現代になって一般家庭にまで普及が実現しました。
その中の一つが、スマート照明です。
その中の一つが、スマート照明です。
この時の坂村教授の研究の核となったアイデアに、HFDS(超機能分散システム:Highly Functionally Distributed System)があります。
これはその後ユビキタス・コンピューティング、Cyber Physical Systems(CPS)などと名称を変えてきましたが、基本的には「コンピュータを使って様々な場所で機能を働かせる」という意味で同じ考えです。
現在ではこのアイデアはIoT(Internet of Things)とよばれており、銀行の送金システムに用いられたり、メルカリ、Airbnb等のサービスアイデアの核となったりしています。
これはその後ユビキタス・コンピューティング、Cyber Physical Systems(CPS)などと名称を変えてきましたが、基本的には「コンピュータを使って様々な場所で機能を働かせる」という意味で同じ考えです。
現在ではこのアイデアはIoT(Internet of Things)とよばれており、銀行の送金システムに用いられたり、メルカリ、Airbnb等のサービスアイデアの核となったりしています。
□まとめ
「現在私たちの生活になくてはならないIoTの起源が、実はスマート照明であった」という驚きの事実がお分かりいただけましたか?
スマート照明はこれからもますます普及することが予想されます。
「現在私たちの生活になくてはならないIoTの起源が、実はスマート照明であった」という驚きの事実がお分かりいただけましたか?
スマート照明はこれからもますます普及することが予想されます。