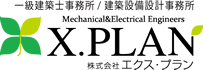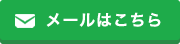省エネ関連
建築物の消費エネルギー計算が必要な理由とは?
2018-05-01
カテゴリ:省エネ計算[概要]
建物を新築・増改築する際、建物の規模に応じて省エネ基準適合義務が発生することを知っていますか?
2017年に施行された建築物省エネ法により、2,000平方メートル以上の非住宅用途の建築物の省エネ基準適合が義務化されました。
では、なぜ日本政府は建築物の省エネルギー対策に力を入れているのでしょうか?
今回は、「建築物に消費エネルギー計算が必要になった背景」を解説していきます。
■その1.「日本がエネルギー効率に高い関心を持っている」
日本はエネルギー効率への意識の高い国です。
それを裏付ける「日本のエネルギー対策・環境問題対策の歴史」が以下の通りです。
日本はエネルギー効率への意識の高い国です。
それを裏付ける「日本のエネルギー対策・環境問題対策の歴史」が以下の通りです。
・「サンシャイン計画」(1974~1993)
新エネルギー技術研究開発についての長期計画です。
新エネルギー技術研究開発についての長期計画です。
・「ムーンライト計画」(1978~1993)
省エネルギー技術研究開発についての長期計画です。
省エネルギー技術研究開発についての長期計画です。
・日本で、省エネルギー法公布(1979)
工場、輸送、建築物、機械器具のエネルギー効率を向上させることを目的とした法律です。
1983、1993、1998、2002、2005、2008、2013年と頻繁に改定を繰り返しています。
工場、輸送、建築物、機械器具のエネルギー効率を向上させることを目的とした法律です。
1983、1993、1998、2002、2005、2008、2013年と頻繁に改定を繰り返しています。
・「ニューサンシャイン計画」(1993~2000)
サンシャイン計画にムーンライト計画を統合した計画です。
サンシャイン計画にムーンライト計画を統合した計画です。
・京都議定書(1997議決2005発行)
気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)で採択され、日本は2008~2012年間の温室効果ガス排出量を1990年比で6%減とする削減目標を掲げました。
気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)で採択され、日本は2008~2012年間の温室効果ガス排出量を1990年比で6%減とする削減目標を掲げました。
・パリ協定採択(2015)
COP21で採択され、日本は2030年度までに2013年度比26.0%減を目標とする「日本の約束草案」を提出しました。
COP21で採択され、日本は2030年度までに2013年度比26.0%減を目標とする「日本の約束草案」を提出しました。
・日本で、建築物省エネ法の施行(2016)
従来の、省エネ法の建築物省エネルギー対策に関する内容に、さらなる制度を加え、新たな法律として公布されました。
従来の、省エネ法の建築物省エネルギー対策に関する内容に、さらなる制度を加え、新たな法律として公布されました。
このように、日本は昔からエネルギー効率について高い関心を持ち、様々な対策を行ってきているのです。
■その2.「建築物に必要なエネルギー消費が増加している」
国内消費エネルギー消費は「輸送」「産業」「民生」と3つの部門に分類されますが、オイルショック以降、省エネルギー対策の成果もあり「産業」「輸送」部門のエネルギー消費量は減少しています。
しかし、家計と第三次産業事業から成る「民生」部門のエネルギー消費量だけが上昇していたことから、政府は建築物の省エネルギー向上に注力するようになりました。
国内消費エネルギー消費は「輸送」「産業」「民生」と3つの部門に分類されますが、オイルショック以降、省エネルギー対策の成果もあり「産業」「輸送」部門のエネルギー消費量は減少しています。
しかし、家計と第三次産業事業から成る「民生」部門のエネルギー消費量だけが上昇していたことから、政府は建築物の省エネルギー向上に注力するようになりました。
その政策の一環で、2015年に『省エネ法』の建築物に関する内容がまとめられた『建築物省エネ法』が公布されました。
今回は、「建築物に消費エネルギー計算が必要になった背景」についてお話ししました。
主に上記の2つの理由から、消費エネルギー計算が必要とされるようになったと言われています。
主に上記の2つの理由から、消費エネルギー計算が必要とされるようになったと言われています。
株式会社エクス・プランは、東京・大阪・松江・米子に拠点を持ち、「建築設備設計・積算業務・省エネルギー措置届出支援業務・CASBEEⓇ申請書作成支援業務」等の業務を行っています。
省エネ計算等でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡ください。